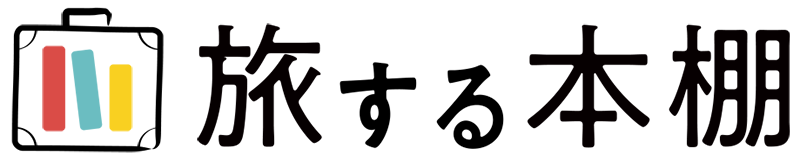【おとなのソロ部】ジブリ映画の舞台も!「江戸東京たてもの園」でタイムトリップ&ひとりレトロ建築さんぽ
新宿から電車とバスで約45分、東京・武蔵小金井にある都立小金井公園の中に位置する「江戸東京たてもの園」は、江戸時代から昭和中期までの歴史的建造物を移築・展示する野外博物館です。日本近代建築の巨匠が手がけた自邸、財閥家の邸宅、さらにジブリ映画の舞台となった商家など、みどころにあふれた園内をひとりでじっくり巡って、レトロ建築を深掘りしてみませんか。明治期の洋館でカフェタイムも楽しめますよ。
歴史的建造物が集まる「江戸東京たてもの園」とは?

JR中央線武蔵小金井駅北口からバスで約5分、緑豊かな都立小金井公園の敷地内に「江戸東京たてもの園」があります。ここは、現地保存が難しい文化的価値の高い建物を移築し、復元・保存・展示する野外博物館で、1993年に開園しました。
園内は西ゾーン、センターゾーン、東ゾーンの3つに分かれていて、江戸時代から昭和中期の建造物が30棟点在しています。見学所要時間は2~3時間ですが、じっくり見て回るならそれ以上みておくのがいいかもしれません。中に入れる建物が多いので、脱ぎ履きしやすい靴で訪れるのがベスト。

マスコットキャラクターは、アニメ監督の宮崎駿さんがデザインした「えどまる」です。宮崎監督のアニメーションスタジオ「スタジオジブリ」は同じ小金井市内にあり、監督は「江戸東京たてもの園」をたびたび散歩で訪れていたそう。映画『千と千尋の神隠し』に登場するいくつかのシーンは、園内の建物を参考にしています。

入口の「ビジターセンター」にあるミュージアムショップには、マスコットキャラクター“えどまる”のグッズをはじめ、オリジナル商品が多数あるので、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
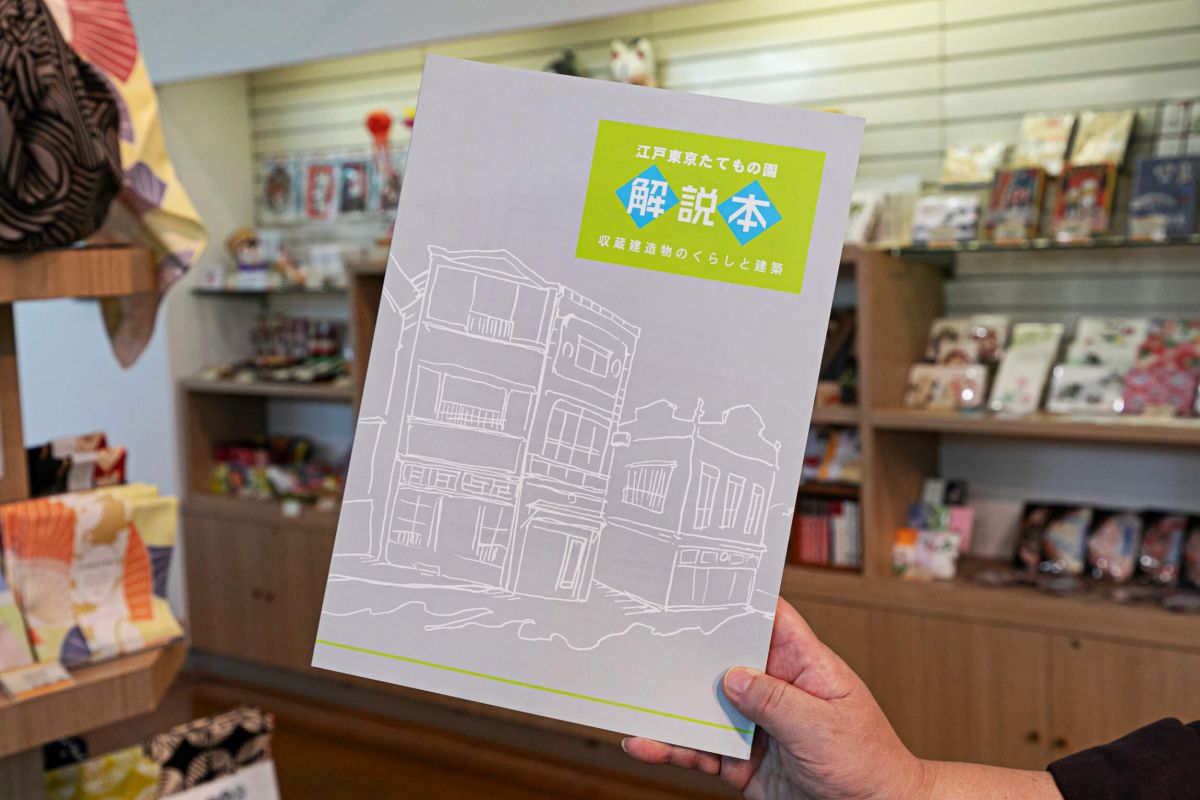
ソロ建築探訪のお供におすすめの書籍をご紹介。園内にある30棟の建造物の概要や構造などを掲載した『江戸東京たてもの園 解説本』。入場時に無料の案内パンフレットはもらえますが、深掘りするにはこの解説本が最適です。リーズナブルな価格もうれしいポイント。
スマホを使った解説を希望する人には、2024年4月にリリースした、鑑賞支援Webアプリケーションの「江戸東京たてもの園鑑賞ナビ」をおすすめします。みどころの解説機能、音声ガイド、現在地や目的地を表示するマップモード、ARモードを搭載。ブラウザ上で作動するアプリなので、簡単で便利ですよ。

オリジナルグッズも気になるところ。全長10cmほどのポールチェーン付き「えどまるマスコット」は大きな目がなんともかわいらしい。ほかにも、建造物の形をした「万世橋交番貯金箱」1600円や、「たてもの園オリジナル 子宝湯エコバッグ」1600円もあります。
さまざま建築様式の住宅が並ぶ【西ゾーン】

ビジターセンターを出ると、エントランス広場が広がっています。その西側は、さまざまな建築様式の住宅を山の手通りとよばれる散策道に面して展示する「西ゾーン」です。
山の手通りを歩いて行くと、大きな門構えの大邸宅を発見。ここは三井財閥の総領家・三井八郎右衞門(みついはちろうえもん)が建てた「三井八郎右衞門邸」です。明治期には六本木に居を構えていましたが、戦災で焼失したため、昭和27年(1952)、西麻布に再建。第11代・三井八郎右衞門高公の死後、「江戸東京たてもの園」に移築・復元されました。建設にあたり、京都の邸宅や大磯の別荘、三井家関連施設から建築部材などが集められたため、財閥が繁栄していた往時を偲ばせる貴重な建築物となっています。

建物正面からは純和風建築に見えますが、西洋文化を取り入れた和洋折衷の邸宅です。玄関にはフランスのガラス工芸家、ルネ・ラリックによるヤドリギがデザインされたボール状の照明が飾られ、2階の仏間前の廊下には煌びやかなシャンデリアを見ることができます。

このシャンデリアはかつて大磯の別荘にあったもので、それ以前は銀行に飾られていたものだとか。天井の高さが足りず、この部分だけ二重折上格天井という、格式のある天井にしています。こんなところにも財閥の富貴さを感じます。


「三井八郎右衞門邸」は、中廊下式とよばれる間取りで、廊下を中心として南側は食堂や客間の生活空間、北側は事務室、厨房といったサービス空間に分かれています。1階の食堂と客間は、明治30年(1897)ごろに京都の「油小路三井邸(あぶらのこうじみついてい)」にあった奥書院の一部を移築したもの。

金色に輝く壁、京都の桂離宮(皇室関連施設)の意匠を取り入れた月の字崩しの欄間……。どちらの天井も格天井になっていて、格子部分には絹に金箔で型押しした草花画がひとつひとつ施され、なんとも美しい。シャンデリアにダイニングテーブル、ソファが配された、京都の雅と西洋文化が混ざり合う空間。和洋折衷の贅の極みが際立っていました。

次に訪れたのは、山の手通り沿いに立つ切妻瓦屋根の「前川國男邸」。

20世紀を代表する建築家、ル・コルビュジエに師事し、日本におけるモダニズム建築を牽引した前川國男の自邸で、昭和17年(1942)に品川区上大崎に建てられました。昭和48年(1973)に解体され、一時は軽井沢にある前川家の別荘に保存、1996年に移築・復元されました。

和風の外観から想像できないほど、内部は洋風モダンなデザイン。約4.5mもの吹き抜けの居間(サロン)を中心に、東側に寝室、西側に書斎を置く間取りで、機能性を重視した木造モダニズム建築となっています。戦時下の資材不足や制限があるなかで竣工したことにも驚きです。

2階分の高さがある格子窓が、より開放的な空間を演出しています。天気のいい日には自然光が差し込み、穏やかな空気に包まれます。彫刻家のイサム・ノグチがデザインした和紙の照明もおしゃれ!

前川國男がデザインしたダイニングテーブルの後ろには、台所に繋がるアーチ型扉、その横には小窓があります。配膳しやすいように、この窓から料理を出していたそうです。タイル貼りの浴室とトイレ、シンプルなデザインの寝室や書斎など、80年以上前に建てられたとは信じられない、圧巻のモダンな住宅でした。
歴史を伝える重厚な建物を展示【センターゾーン】

入り口の「ビジターセンター」とその東側は、歴史を伝える建物が集まる「センターゾーン」。なかでも、明治から昭和の初めに活躍した政治家・高橋是清の邸宅は、二・二六事件の舞台にもなった場所です。是清の死後、主屋部分は府中市の多磨霊園に移築、1993年に「江戸東京たてもの園」に移築・復元されました。
「高橋是清邸」の特徴は、化粧材として高級木材のツガを使用する「総栂普請(そうつがぶしん)」とよばれる和風邸宅ですが、1階には寄木張りの床板を敷く洋間もあります。「三井八郎右衞門邸」も含め、明治維新後の西洋文化を建物にも取り入れる流れであることが分かります。

建物の至る所で見られる窓ガラスは、当時のものがそのまま使われています。和風建築に用いられた初期のガラスで、波打つようなゆがみは現在では作るのが困難だそう。


2階は高橋是清の寝室や書斎として使われていました。柱が少なく、開放的な空間で庭園の眺望も楽しめます。木枠の美しい窓と植物の緑を風景に取り入れた写真が撮れる絶好のフォトスポットですが、是清が暗殺された二・二六事件の舞台でもあり、歴史の重みを感じられます。
下町風情を感じるレトロな街並み【東ゾーン】


「センターゾーン」の東側に位置する「東ゾーン」は、江戸末期から昭和にかけて建てられた商店や銭湯、居酒屋、旅館などが立ち並ぶ、レトロな町並みが広がるエリアです。建物の中も当時の様子を再現しているので、古きよき時代の生活を建物の内部からも体感できます。

注目すべきは関東大震災後の東京で流行した、看板建築とよばれる建築スタイル。正面にタイルや銅板を貼り、一枚の看板のように装飾した店舗併用住宅で、自由な発想でデザインされ、どの建物も個性的。洋風にまとめられた「植村邸」は銅板で装飾されたアーチ部分の飾りがおしゃれです。

「大和屋本店(乾物屋)」は看板建築の特徴と出桁造り(だしげたづくり)とよばれる伝統的な商家の意匠を取り入れたユニークな造りで、店舗前面にあったタバコ屋も再現しています。

ファサードに古代ギリシア建築様式のひとつ、イオニア式の柱を並べた「村上精華堂(化粧品屋)」。

当時は香油やクリーム、香水などを店の奥で作っていたそう。店内は和の空間で、外観の個性的な洋風装飾とのギャップに驚きます。

「花市生花店」は建物正面に花や蝶をあしらった銅板のレリーフが見られます。側面上の一部に銅板が張られているのは、隣に2階建ての建物があったから。関東大震災後の復興期に誕生した看板建築は火に強い銅板やモルタルを使用することで、防火対策も徹底していました。

隣に立つ前面タイル張りの「武居三省堂(文具店)」は、店内もみどころ。左右の壁や上部に棚を設け、収納スペースを確保する、工夫を凝らした造りです。ジブリ映画『千と千尋の神隠し』で、釜爺がいるボイラー室の薬草棚のモデルにもなっています。

「丸二商店(荒物屋)」は側面にも銅板で装飾された二面ファサードで、屋根の上端部の柱なども凝った造り。

店内には食器やホウキ、タワシなど日用雑貨が並んでいて、懐かしい雰囲気。ふと外を見ると黄色い路面電車(屋外展示物の都電7500形)が見えて、昭和時代にタイムトリップした気分。

下町中通りの奥に威風堂々とたたずむのは、昭和4年(1929)に足立区千住元町に建てられた銭湯の「子宝湯」。

東京の銭湯を代表する贅を尽くした建物で、入母屋(いりもや)造りの大屋根、玄関上には社寺建築に用いられる唐破風(からはふ)、その下には宝船に乗った七福神の彫刻もあって、外観だけでも豪華な造りなのが分かります。

のれんをくぐり、下駄箱に靴を入れて脱衣所へ。天井が高く開放的で、格子状の天井は中央部を持ち上げた「折上げ格天井」になっています。本来、格の高い部屋だけ使うものだった格天井を庶民の銭湯にも用いているなんて……。銭湯を建てる当時の相場は2万円弱のところ、「子宝湯」は4~5万を費やしたようで、施主の気合いを感じます。

浴場を彩るのは銭湯の代名詞ともいえるペンキ絵。男湯に富士山、女湯は遠景が描かれています。

洗い場には昔話の一場面を描いたタイル絵があり、なんともユニーク。浴槽は3つに分かれていて、小さい浴槽はくすり湯だったそう。昭和28年(1953)当時の入浴料は大人15円、髪を洗うための婦人洗髪料別途10円。当時も都内一律の入浴料金なので、それなら贅を尽くした「子宝湯」に一度は訪れてみたくなりますね。
明治期の洋館「デ・ラランデ邸」でカフェタイム

「西ゾーン」にある復元建造物「デ・ラランデ邸」では、1階の食堂と居間、テラスが、カフェ「武蔵野茶房」としても利用されています。レトロ建築を楽しみつつ、優雅にカフェタイムはいかがでしょうか。
新宿区信濃町にあった「デ・ラランデ邸」の前身は、物理学者・北尾次郎(きたおじろう)が設計した木造平屋建ての洋館。明治43年(1910)にドイツ人建築家のゲオルグ・デ・ラランデによって3階建てに増築されました。その後、何度か所有者が変わり、昭和31年(1956)からは乳酸菌飲料で知られるカルピスを発明した三島海雲(みしまかいうん)の住居となりました。現在見られる建物は、デ・ラランデによる増築が行われたころに復元され、室内は古写真を元に、デ・ラランデが暮らしていた大正初期の様子に再現されています。

白漆喰の格天井に、石膏のレリーフ、シャンデリアが素敵な食堂でカフェタイム。

おひとりさまならベイウインドウ(張り出し窓)側の2名掛けテーブルがおすすめ。フラワープリントの壁もロマンティックでより優雅なひとり時間を過ごせそう。

カルピスを発明した三島海雲にちなんだ、ひんやりメニュー「カルピス®シャビアン」は、フローズンカルピスにソルティーレモンを合わせた、暑い夏にぴったりなドリンク。夏はレモン、秋は巨峰と、季節ごとのフレーバーを楽しめます。

スイーツ好きなら「特製おいものパフェ」はいかが。温かいスイートポテトに芋甘納豆、あんこ、生クリーム、仕上げにソフトクリームをどーんとのせた、歩き疲れた体に染みるボリューミーな温冷スイーツ。

氷をコーヒーで作った、溶けても薄まらずにいただけるアイスコーヒーもぜひ。陶器とガラス瓶を使った、見た目にもこだわったドリンクです。
震災や戦災で多くの建造物が失われた東京で、文化的価値の高い建造物を保存・展示する「江戸東京たてもの園」。ファサードの装飾、屋根の形、建物内の天井など、時代ごとに異なる建築が見られる貴重な野外博物館でした。自分のペースでゆっくり見学できるソロ建築探訪にぜひトライしてみてください。
■江戸東京たてもの園(えどとうきょうたてものえん)
住所:東京都小金井市桜町3-7-1 都立小金井公園内
TEL:042-388-3300
営業時間:9時30分~17時30分(10~3月は~16時30分、入園は閉園の30分前まで)
定休日:月曜(祝日または振替休日の場合は翌日)
料金:400円
■おすすめの利用シーン:レトロな雰囲気を楽しみたいとき、名建築をじっくり鑑賞したいとき、カフェでゆっくり過ごしたいとき
Text:木村秋子(editorial team Flone)
Photo:yoko
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。