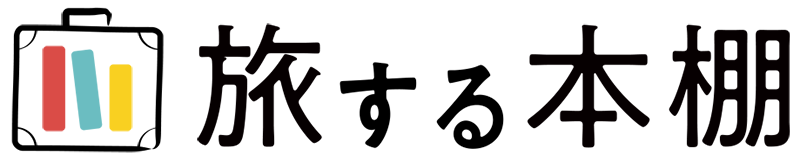「鉱石の道」って知ってる?日本の近代化を支えた兵庫の街をご紹介!
みなさんは金属がどのようにできるのか、ご存じですか? 兵庫県・但馬(たじま)地区の朝来市(あさごし)と養父市(やぶし)にまたがる4つの鉱山では、近年まで鉱石の採掘が行われていたんです! 今回ご紹介するのは、日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」。そのなかでも鉱石の道に注目して、金属になるまでのストーリーとそこに携わった人々の足跡をたどってみましょう!
日本遺産ってなに?

今回ご紹介する「鉱石の道」は、「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」として兵庫県の「日本遺産」に登録されています。そもそも「日本遺産」とは何なのでしょう? 「日本遺産」とは、文化庁が認定する、日本国内の各地域の歴史的経緯や、風土に根ざした伝承、風習などを踏まえたストーリーと有形・無形の文化財をパッケージ化したものです。例えば上の写真は、鉱石の道のなかでも特に有名な「生野銀山」の鉱山町の様子。「日本遺産」は、そのストーリー性を重視することで、個別の建造物や遺跡などはもちろん、それぞれの背後にある地域の歴史・文化・風土などについても知ることができるんです!

現在、日本には104カ所の「日本遺産」が登録されています。そのうちの一つ「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」も、背景に「日本遺産」に認定されるのにふさわしいストーリーを持っています。この地域を訪れて、ストーリーに触れることで、「日本遺産」がどのようなものなのかについても、より深い理解が得られるはずです。
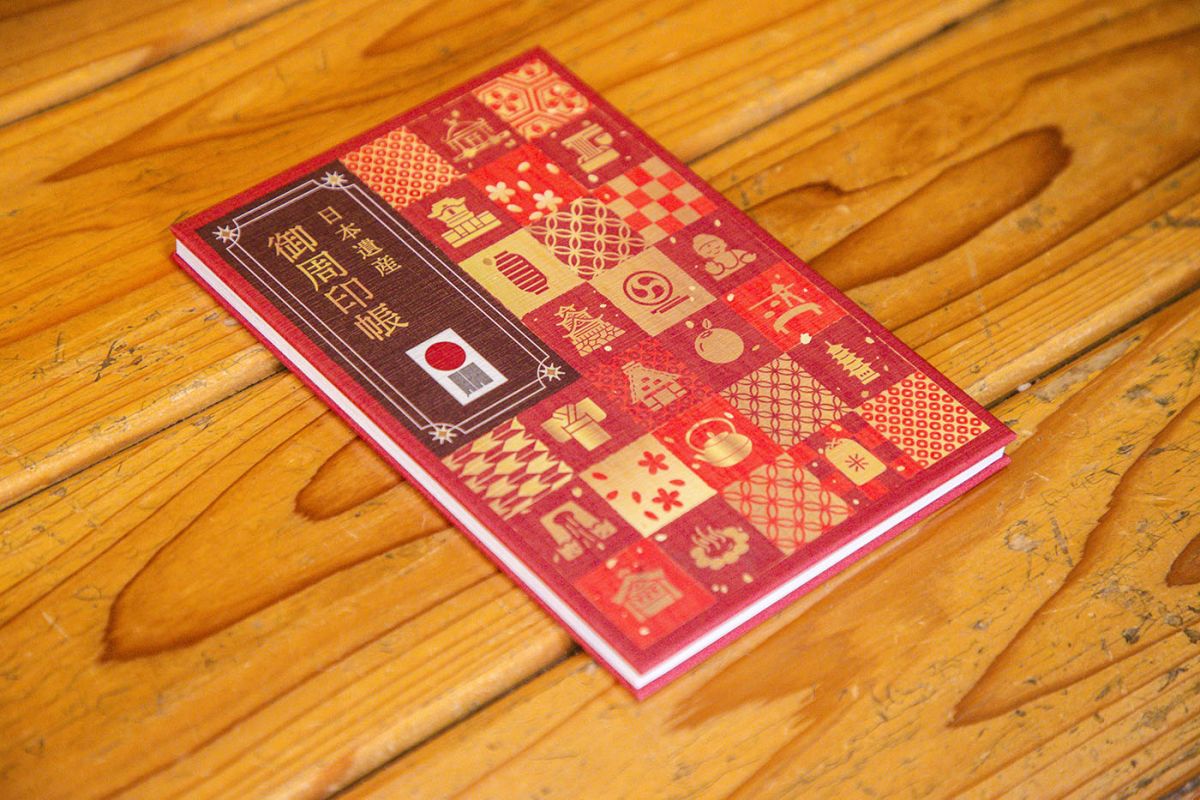
日本観光振興会では、文化庁が認定した「日本遺産」104カ所において、その来訪の証として「御周印」がもらえる、御朱印帳ならぬ「御周印帳」を発行しています。新しいデザインの「御周印」を2025年4月1日(火)より全国各所で販売開始予定です。

御周印を集めながら、日本中の「日本遺産」を巡り、それぞれが持つストーリーに触れることで、同時に自分自身の人生もどんどん豊かになっていくことが実感できるはず。日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」では、JR生野駅構内にある朝来市観光情報センターで御周印をもらうことができます(2025年4月1日(火)より有料化予定)。「御周印」の詳細や「御周印帳」の取得方法については、下記ボタンからチェックしてみてください。
日本の近代化を支えた「鉱石の道」をたどってみよう!

日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」は、兵庫県の播但(ばんたん)地域を南北に貫く、全長73㎞に及ぶ道です。この1本の道は、姫路・飾磨港(しかまこう)から生野鉱山(いくのこうざん)へと続く「銀の馬車道」と、生野鉱山からその奥にある神子畑選鉱場(みこばたせんこうじょう)・明延鉱山(あけのべこうざん)・中瀬鉱山(なかぜこうざん)へと続く「鉱石の道」の大きく2つに分かれます。

播磨の飾磨港(現姫路港)と生野鉱山の間、約49㎞を結ぶ馬車専用道路として建設されたのが、日本初の高速産業道路といわれる“銀の馬車道”です。鉱山の採掘・製錬に必要な機械や日用品などの物資と産出された金・銀・銅などの鉱石を輸送するルートとして整備されたものですが、今回は、その先・生野鉱山から中瀬鉱山まで続く約24㎞の「鉱石の道」をご紹介します。
日本一の錫の産出量を誇った「明延鉱山」

「鉱石の道」は、その一番奥から順に中瀬鉱山→明延鉱山→神子畑選鉱場→生野鉱山の順に並んでいますが、今回は、明延鉱山をスタートして生野鉱山まで進む、鉱石が金属になるまでの流れに沿ったルートをご紹介します。
明延鉱山は、奈良東大寺の大仏を鋳造する際に、明延産出の銅が使われたと伝えられるほど歴史の古い鉱山です。昭和62年(1987)に閉山となりましたが、現在は「明延鉱山 探検坑道」として坑道の一部が一般公開されているほか、鉱山町としての町並みも保存されています。

明延鉱山は江戸時代には江戸幕府の下で、明治時代には明治政府の下で盛衰を繰り返しましたが、明治29年(1896)に民間企業の三菱に払い下げられ、その後、錫(すず)の鉱脈が発見されたことで「日本一の錫の鉱山」として大きく発展することになります。

坑道の総延長は、なんと550㎞にも及びます。東京〜大阪間の距離に匹敵するもので、約5㎢の範囲のなかで、深さ約1000mまで掘り下げられています。その途方もないスケールは、探検坑道として公開されている約650mを歩くだけではなかなか理解できませんが、ガイドさんの分かりやすい話を聞きながら、さまざまな説明を受けるなかで、少しずつですが、当時の坑道内の風景がイメージできるようになっていくから不思議です。

探検坑道の中には、地中深くまで続くエレベーターや、当時使われていた重機などが展示されていたり、巨大な鉱脈の跡などがあったりと、みどころ豊富です。写真の酒蔵「明壽蔵(めいじゅぐら)」もその一つで、坑道内の温度が年間を通して12~14度前後と安定していることから、現在は日本酒の熟成に利用されているという珍しい光景も見られます。坑道見学は近隣の「あけのべ自然学校」へ3日前までに予約が必要です。
■明延鉱山 探検坑道(あけのべこうざんたんけんこうどう)
住所:兵庫県養父市大屋町明延1184
TEL:079-668-0258(あけのべ自然学校)
料金:大人・高校生1200円、小・中学生600円
※3日前までに電話で要予約
明延鉱山と神子畑選鉱場を繋いだ「一円電車」

明延鉱山で掘り出された錫などが入った鉱石は、その時点ではまだ岩の塊です。これを金属にするためには、ここからさらにさまざまな工程を踏まなくてはなりません。昭和4年(1929)に開通した明神軌道は、明延で採鉱された鉱石を選鉱という次の段階へ進めるために、神子畑へと運ぶ約6㎞の鉄道です。昭和20年(1945)からは鉱山従業員の通勤電車としても利用され、当時乗車料金が1円であったことから「一円電車」とよばれるようになりました。

一円電車は、探検坑道から徒歩約5分の「あけのべ一円電車広場」に展示されています。鉱石を運ぶ列車なので、少しゴツいものを想像していましたが、意外にも、中も外もとてもかわいらしい見た目が印象的でした。一円電車の体験乗車ができるイベントも不定期で開催されているので、そちらも要チェックです。
東洋一の選鉱場「神子畑選鉱場」

明延鉱山で掘り出された鉱石は、明神軌道で神子畑選鉱場に運ばれます。神子畑には元々、平安時代に開山したと伝えられる歴史ある鉱山があり、銀の採鉱などが行われていましたが、明治40年(1907)以降は鉱脈が減少、明治42年(1909)に明延鉱山で錫鉱脈が発見されたこともあって、神子畑鉱山は神子畑選鉱場に生まれ変わりました。まるで古代神殿のような巨大な構造物は選鉱場の跡で、コンクリートの基部の上には当時、選鉱場の建物が建っていました。

神子畑に到着した鉱石は、高低差75mの選鉱場でその落差をうまく利用して、上から順に岩を砕いて小さくしていき、最後は液体のような状態にする選鉱という作業を行います。さらに、この微細な個体が混じった液体を写真のシックナーという装置で水と固体に分離して、金属だけを取り出すのです。神子畑選鉱場とシックナーのインパクトある景観は、この地を訪れた人を圧倒する、必見の産業遺産です。

神子畑選鉱場のたもとにたたずむおしゃれな洋館は「ムーセ旧居」とよばれる建物で、生野鉱山開発に貢献したフランス人技師のムーセの元住居です。明治21年(1888)に生野から神子畑に移築され、事務舎として利用されていましたが、現在は建物内で当時の資料などを展示しています。
■神子畑選鉱場跡(みこばたせんこうじょうあと)
住所:兵庫県朝来市佐嚢1842-1
TEL:079-666-8002(鉱石の道神子畑交流館「神選」)
営業時間:見学自由(施設内は立ち入り禁止)
■ムーセ旧居(むーせきゅうきょ)
住所:兵庫県朝来市佐嚢1826-1
TEL:079-666-8002(鉱石の道神子畑交流館「神選」)
営業時間:10〜17時
定休日:水曜
日本最古の鋳鉄橋を渡ってみよう!

神子畑で選別された金属の粒子のうち、銅は瀬戸内海の直島へ、亜鉛は遠く秋田に運ばれ製錬され、私たちが知る金属の塊になります。そして明延鉱山の主力でもある錫は神子畑から生野へと運ばれ、そこで金属の塊(インゴット)に生まれ変わります。
神子畑から生野銀山へと向かう鉱石運搬道路の途中にも、国の重要文化財に指定されている歴史的な建造物が見られます。それが、日本一古い全鋳鉄製の橋といわれる「神子畑鋳鉄橋」です。

明治16年(1883)〜18年(1885)頃、フランス人技師の指導により設計から施行まですべてを日本人が行ったもので、現在もこの橋を歩いて渡ることができます。造られてから140年近くが経とうしているのに、その上を歩いても微動だにしない頑丈さに、当時の技師たちの技術力の高さがうかがえます。
■神子畑鋳鉄橋(みこばたちゅうてつきょう)
住所:兵庫県朝来市佐嚢1637-7
TEL:079-677-1165(朝来市観光協会)
鉱山町のレトロな邸宅でホッとひと息

生野銀山から車で約7分の場所に、当時鉱山町として、採掘に関わる役人や商人、鉱夫たちが生活していた町があります。口銀谷(くちがなや)とよばれるその町には、今も当時の面影を残す多くの史跡が残されています。町を流れる市川(いちかわ)沿いにはトロッコの軌道跡が見られ、町の中では銅などを製錬するときにできたカスを固めた「カラミ石」が家の土台や塀に使用されている風景も見ることができます。

口銀谷にある「口銀谷銀山町ミュージアムセンター」にも立ち寄ってみました。建物は生野の歴史にゆかりの深い浅田家と吉川家の古民家を活用したもので、昭和初期の和風建築と大正期のタイル張りの洋館が共存する独特の雰囲気が特徴です。

建物内は自由に見学して展示されている資料などを見ることができます。またレトロモダンな雰囲気が心地よい空間は、カフェとしても利用できます。
■口銀谷銀山町ミュージアムセンター(くちがなやぎんざんまちみゅーじあむせんたー)
住所:兵庫県朝来市生野町口銀谷619-2
TEL: 079-670-5006
営業時間:9〜17時
定休日:月曜
料金:無料
開坑1200年の歴史を誇る生野銀山

明延鉱山で採鉱された錫は神子畑で選鉱され、生野で製錬されて晴れて金属として世に出回ることになります。生野は元々、大同2年(807)に銀が出たと伝えられる歴史ある銀山。現在は坑道の一部が「史跡生野銀山」として一般公開されています。

生野銀山の総延長は約350㎞、地下は880mの深さまで達します。そのうちのほんの一部、約1㎞の近代鉱山を観光坑道として見学することができます。往復約40分のコース内には、採鉱作業を再現した人形や、重機類などが展示されており、近世から近代までの作業の移り変わりを分かりやすく紹介しています。

明治元年(1868)に日本最初の官営鉱山となった生野銀山は、西洋から最新の鉱山設備が導入されるなどして飛躍的に発展し、日本の近代化をけん引する模範鉱山となっていきました。明治29年(1896)には三菱合資会社に経営が譲渡され、ピーク時の明治30年(1897)には生野の人口も1万1000人を超えていました。

坑道内はみどころ豊富で、江戸時代に行われていた生々しい手掘りの跡や、近代化が進むなかで使用されたさまざまな機器などを見ることができます。写真の巨大な巻揚機もその一つで、当時エレベーターとして使用されていたものです。

昭和30〜40年代、生野鉱山の社宅でよく食べられていたのがこちらのハヤシライスです。写真の「ハヤシライス」は、「道の駅 フレッシュあさご」で提供されているメニューですが、生野周辺には各家庭で食べられていた復刻版のハヤシライスを提供する店も点在しているそう。生野に来たら名物のハヤシライスもぜひ味わってみてください!
■史跡生野銀山(しせきいくのぎんざん)
住所:兵庫県朝来市生野町小野33-5
TEL:079-679-2010
営業時間:9時10分~17時20分(季節により変動あり)
料金:大人1200円、小中高校生600円
定休日:12~2月の火曜(祝日の場合は翌日)
「鉱石の道」の旅のお供にぜひ活用したいアプリをご紹介!

「鉱石の道」をたどった今回の旅ですが、旅のお供にぜひおすすめなのが、JR西日本が提供する北陸・せとうち・山陰エリアで利用できる観光ナビサービス「tabiwa」。スマホにアプリをダウンロードするだけで、さまざまな施設で割引などお得なサービスが受けられたり、観光スポットの情報が得られたりします。今回ご紹介した各施設も登録されているので、おでかけの際にはぜひ、あらかじめアプリをダウンロードしておいてください!

いかがでしたか?「鉱石の道」をたどる旅は、鉱山で鉱石が掘り出されてから金属になるまでの流れを知ると同時に、多くの人の力が結集されると、そこに途方もないエネルギーが生まれ、想像をはるかに超えるようなスケールのプロジェクトが進行することも感じ取れるはず。日本の近代化の歴史そのものをたどる「鉱石の道」は、感動のストーリーを体感する旅でもありました。
Text&Photo:能勢太郎(Clay)
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
Sponsored:北近畿広域観光連盟