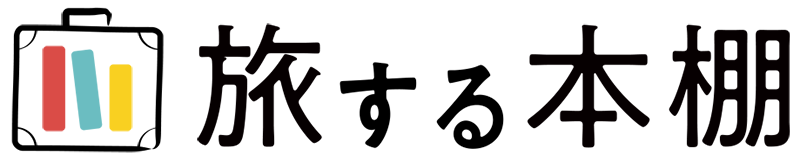【おとなのソロ部】大阪「NISHIGUCHI KUTSUSHITA STORE OSAKA」で一度履くと手放せなくなる“はくひとおもい”の靴下に出合う
1950年から靴下づくりを続ける日本のファクトリーブランド「NISHIGUCHI KUTSUSHITA(にしぐちくつした)」の噂を聞いて、大阪の長堀橋にあるショップを訪れてきました。天然素材にこだわり、毎日の暮らしを快適にする“はくひとおもい”な靴下たち。履く人のためを追求した履き心地と時代に捉われないデザイン、良心的な価格を実現し、一度履くと手放せなくなる人が続出です。お手入れ方法も紹介しているので、最後までチェックしてくださいね。
履く人のことを真面目に考えてつくる靴下ブランド「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」

靴下をデザインだけで選ぶと、履き心地がしっくりこなかったことはありませんか。締め付けがきつかったり、むれてしまったり、足が冷えてしまったり。そんなとき「一度履くと手放せなくなるよ」とおすすめされたのが「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」です。

「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」は“はくひとおもい”をコンセプトに、天然素材・編み方・質感にこだわり、何度も試作を重ねて定番のソックスをつくる奈良・葛城市発のファクトリーブランドです。
実際に履いてみると、「靴下ひとつでこんなに毎日が快適になるんだ」と感動しました。デザインはシンプルでカラーリングも素敵なので、どんなファッションにもマッチするものが見つかるはず。一足1000〜2000円台という日常づかいしやすい価格帯も魅力的です。
破れにくく暖かく、いかにも冬らしいウールジャガードソックス

店内に入って、いちばんにこのかわいいウールソックスに目が惹きつけられました。ふっくらボリュームのある、いかにも暖かそうなソックス。あえてパンツの裾からちらりとのぞかせてアクセントにしたくなるようなカラーリングとトラッドな柄もお気に入り。

この靴下には、従来のウールのソックスにはなかった強度をもたせたところに大きな特長があります。温かくてやわらかい風合いを保ちつつも、ウールとナイロンをほどよくブレンドして、通常の2倍程度の強度が得られる靴下を開発したといいます。これは通常靴下の編み立てでは行なわない糸の組み合わせ。さらにウールの伸縮性を考慮したサイズ調整に加え、摩擦が大きなかかとに強度をもたせるようにデザインを変更しました。

“最強の定番”を生み出すため、細やかに修正を加えてバージョンアップしていくのが「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」の大きな特長です。また、通常靴下の編み立てでは行なわない糸の組み合わせにたどり着いたように、靴下業界の常識ではあり得ない製法 も、履く人の快適を考え抜いたからこそ発見できたというから驚きです。
毎日履きたくなる最高にベーシックな「エジプトコットンリブソックス」

「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」の前身である西口靴下は、靴下の一大産地・奈良県の葛城市に1950年から靴下づくりを続けるファクトリーから生まれました。3代目の西口功人さんは、製造工場だからこそできる靴下づくりをするため「はくひとおもい」というコンセプトを軸に、自社ブランドを立ち上げました。
2017年3月にブランドを立ち上げて「シンプルに優等生のようなストレートなコットンの靴下を作りたい」と開発したのが「エジプトコットンリブソックス」です。これはまさに「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」の代表作。

西口さんはどのようなコットンを使えば、もっとも上質でベーシックな靴下になるかを探求しました。いろいろな糸を試したところ、「綿のカシミヤ」とも称されるエジプトの「ギザコットン」と出合い、その中でも繊維が長く、よりを甘くかけても 糸としての強度を保つことができるものを選びました。
この独特の光沢のある美しい色をどう編み上げればいいのか、西口さんの長い検証の日々が始まります。ローゲージと呼ばれる厚手の靴下の編み機で作ってみても、糸の良さを最大限に生かすことができません。度重なる試行錯誤を経て、 通常よりも糸を機械に多く投入して編むことで、ようやく独特のモチモチとした風合いを出すことができたそう。
西口さんの靴下人生の中で、「もっとも糸のよさを引き出せた」と言わしめる最高傑作。それがこの「エジプトコットンリブソックス」です。実際に履いてみると、肌触りが抜群。伸縮性のあるふわふわの履き心地で、しっかり厚みがあるため足が疲れにくいです。

「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」のど真ん中・エジプトコットンリブソックスを薄手にしたのが「エジプトコットンプレーンソックス」です。春に薄手のコットンの靴下をスニーカーに合わせておでかけしてほしい。そんな想いのもと生み出された靴下は潔いほどにシンプル。白などのベーシックなカラーはもちろん、赤はトレンチコートなどの春の装いの差し色になりそう。

履き心地はふわっとやわらかく、肌触り抜群! するっとスムースで心地よく、春先のわくわくとした気持ちにそっと寄り添ってくれます。
素材や編み方を駆使して、暮らしをアップデートする靴下を生み出す

天然素材の糸には節があったり、切れやすかったりするため、量産型の編み機では編むことが難しいことも。そこでオールドマシンを駆使できるのも「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」の強みです。古い機械の扱いは難しいそうですが、高い技術力があれば天然素材の編みを可能にする細やかな調整ができます。

「シルクコットン天竺ソックス」は、エコシルクとリサイクルコットンを使用した味わい深い靴下。紡績時に糸にならなかったコットンを特殊な紡績機にかけたリサイクルコットンとシルク紬糸の組み合わせです。

履き口とつま先と切り替えがなんともかわいいですよね。シルクらしいしっとりとした風合いと、コットンのやわらかさのいいとこどり。

締まりすぎず、さらりとした履き心地が気持ちいい。シルクの吸湿性の高さで蒸れにくく、夏場でもさらっとします。快適に過ごす毎日が最高の贅沢、とはまさにこのこと。

おうち向けに、温かく締め付け感がない最高のホームソックスを見つけました。「シルクコットンホームソックス」です。 肌側がシルクコットンのパイル、外側がコットン、中間層に伸縮糸を使用した三層パイルという技術が使われています。この技術は一人の職人が機械の調整を少しずつ改良し、三年かけて開発した編地がベースとなっているそうです。
肌側をあえてシルクコットンにすることも大きなポイント。シルク100%の場合、使用を繰り返すとパイル地が硬くなることを防ぐため、シルクとコットンを50%ずつブレンドした糸を使用しました。洗濯に強くやわらかいコットンの風合いに、シルクのしっとりとした保湿性と吸湿性をプラスした、最強のおうちソックスが仕上がりました。
修繕技法・ダーニングやお手入れ方法を紹介

「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」では素材の選定や編み方に工夫を重ねていますが、ウールの靴下などは摩擦に弱く、着用し続けると破れてしまうこともあります。ショップではお気に入りの靴下が破れてしまったときのために、ダーニングの道具も扱っています。ダーニングとはヨーロッパに伝わる手法で、穴やシミを隠すだけでなく、カラフルな糸を組み合わせて修復するのでデザインのアクセントになります。

さらに公式サイトでは各靴下のお手入れ方法やダーニングの動画も公開されています。長く履き続けるためにダーニングで修復すれば、世界にひとつしかない靴下が生まれて、いっそう愛着が湧きそう。

はくひとおもいな「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」はいかがだったでしょうか。クチコミでそのよさが広がるのも納得の履き心地で、すっかりファンになってしまいました。シーズンによって限定色が発売されるのも特長で、公式ホームページで読める「シーズンカラーストーリー」もおすすめです。西口さんが旅した場所で見つけた心に残る色。その色合いがシーズン限定で靴下を鮮やかに彩ります。2025 SPRING &SUMMERシーズンカラーも公開されたばかりですので、公式サイトをぜひチェックしてみてくださいね。
「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」のシンボルはハートの形によく似た「ソックハート」。ラッピングの袋にもソックハードがデザインされていて、贈る人にいくつものハートをそっと届けてくれます。靴下を履いている時間って、結構長いですよね。その時間を心地よくストレスフリーにするだけでご機嫌になれることを実感します。オンラインでも購入できますが、大阪のほか、東京・浅草橋にも店舗があるので、ぜひお店で実物にふれてみてくださいね。
■NISHIGUCHI KUTSUSHITA STORE OSAKA(にしぐち くつした すとあ おおさか)
住所:大阪府大阪市中央区南船場1-17-21 長堀ビル103
TEL:070-1745-9900
営業時間:11〜19時
定休日:不定休
アクセス:Osaka Metro長堀橋駅から徒歩2分
■おすすめの利用シーン:自分に合った靴下を見つけたいとき、とにかく履き心地のいい靴下を探しているとき、シーンに合った靴下を見つけたいとき、誰かに喜ばれる贈り物したいとき
Text:鴨 一歌
Photo:沖本 明、一部NISHIGUCHI KUTSUSHITAより提供
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
●「LINE」は、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。