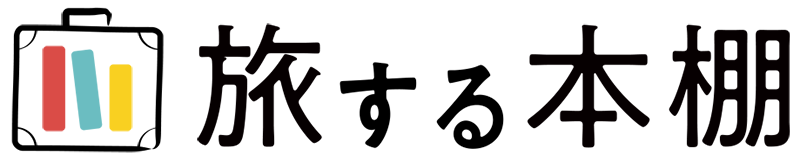「旧岩崎邸庭園」で華やかな明治時代を体感。麗しい洋館を愛で、風情ある和館で抹茶をいただく
明治時代の実業家である岩崎久彌(いわさき ひさや)の本邸として、明治29年(1896)に建てられた「旧岩崎邸庭園(きゅういわさきていていえん)」。設計は多くの日本人建築家を育てたジョサイア・コンドルによるもので、広大な庭園は江戸時代の大名屋敷がルーツ。どこを切り撮っても絵になる空間です。岩崎家の生活の場として用いられていた数寄屋風書院作りの和館の一部は甘味処となっており、抹茶や和菓子をいただくこともできます。
湯島駅から徒歩3分。明治時代の豪華絢爛な邸宅

東京・上野の閑静な場所に広大な敷地を持つ「旧岩崎邸庭園」。東京メトロ千代田線湯島駅から徒歩約3分、東京メトロ銀座線上野広小路駅から徒歩約10分、JR線御徒町駅から徒歩約15分、JR線上野駅から徒歩約20分と、さまざまな路線からアクセスすることができます。
設計は、多くの日本人建築家を育てたジョサイア・コンドルによるもの。現在では、当時の上流階級の暮らしを伝える貴重な文化財として、一般公開されています。まずは受付で入園券を購入し、中へと入ります。


「旧岩崎邸庭園」の正面玄関へと続く道には、「馬車道」と書かれた立て看板があります。これは、明治時代の当時に馬車で行き来していた道であることから。現在は歩いてここを上り、洋館の正面玄関へと行きます。ゆるやかな坂になっていますが、道沿いに咲く季節の花々を眺めつつ、楽しみながら上りましょう。馬車でこの道を通っていたなんて、当時の華やかな生活が想像されますよね。


馬車道を5分ほど歩くと、「旧岩崎邸庭園」が見えてきました! 手前に広がる木々もみどころです。夏の新緑、秋の紅葉と、四季折々でさまざまな表情を楽しめます。樹齢400年以上という立派なイチョウの木もあり、秋に美しい姿を見せてくれます。
建築当初は約1万5000坪の敷地のなかに20棟以上の建物があったそうですが、現在は東京都が管理する都立庭園として、当時の敷地の半分弱が公開されています。

正面玄関から見上げると、ジャコビアン様式の影響を受けているという、重厚感と繊細さが見事に融合した建築美に息を飲みます。少し立ち止まって、じっくりと明治時代の最先端の西洋建築技術を観察してみるのもいいですね。
ディテールも美しい内装をじっくりと堪能

文化財の保護のため、見学する際は靴下を着用のうえ、靴を脱いで上がります。

重厚な木製の扉の上部にあしらわれた、正面玄関のステンドグラスもみどころ。これも建物の設計を手がけたジョサイア・コンドルによるもの。庭園の緑を映し出せるように、ステンドグラスによく見られる鮮やかな色彩をあえて付けていないそうです。


正面玄関の床に敷かれているタイルにも注目です。目地がなく、繊細な美しさ。美しいタイルが玄関以外にもベランダの床や暖炉周辺など、館内の随所に使用されています。

玄関ホールにあるスチームヒーターは当時最先端の暖房技術としてアメリカから導入されたものだそうです。現在は使われておりませんが、当時のまま残っています。


洋館の見学は、順路の通りに進みます。こちらが、洋館1階のホール。写真中央に見える柱は地下から2階まで続くもので、中に鉄柱が通っている岩崎邸の大黒柱です。左の階段は元々は柱がなく壁付けの空中階段だったそう。当時はこの階段を下りると、通常非公開の地下道を通って別棟の撞球室(どうきゅうしつ=ビリヤード場)へと行くことができたそうです。

洋館1階にある暖炉の上の鏡は、かなり高い位置に設置されていて姿を写すことができません。この鏡は人を写すためでなく、お部屋を広く見せたり明るくしたりする用途があったそうです。暖炉は各部屋にあるので、装飾の違いを見比べるのも楽しいですね。

こちらが、洋館1階の婦人客室。設計者であるコンドルが好んでいたという、イスラム風のデザインが取り入れられており、暖炉のデザインもイスラム風です。当時、社交界では食事前後などに男性女性が分かれて過ごす文化があったため、男性は撞球室で、女性はこの部屋でくつろいで過ごしたとか。
また、婦人客室には、岩崎家で使われていた来客用のガラス食器の一部が展示されています。すべてフランス・バカラ社製で、桜や松模様が彫刻されたものは、岩崎家が特注したものといわれています。


こちらは、明治後期に増築されたといわれるサンルーム。窓ガラスの一部は、当時のふきガラスがそのままはめこまれており、ところどころにゆがみが見られます。サンルームの下には、洋館と撞球室をつなぐ地下道が設けられています。

サンルームの窓からは、井戸のような四角形の石組が見えます。これは、地下道のための通気口。写真右に見えるガラスの部分は、地下道に採光するように作られた窓です。

こちらが、撞球室。中に入ることはできませんが、外から眺めることは可能。当時はここで男性たちがビリヤードをして楽しみました。開放的な天井からは、また洋館とも違った、洗練された趣が感じられます。

洋館1階の婦人客室の隣には、書斎があります。「旧岩崎邸庭園」は、通常は客人を迎える迎賓館として使われていましたが、この書斎だけは、家主の岩崎久彌が普段から使用していた部屋だそうです。


次は、客室や集会室がある2階へ。壁紙に使われているのは、岩崎邸のシンボルでもある伝統工芸品の金唐革紙(きんからかわし)。「旧岩崎邸庭園」では部屋ごとに色味やデザインの趣がすべて異なります。現在はじゅうたんが敷かれているため見えないですが、床の寄木も各部屋によってデザインが異なっていたとか。各部屋の壁にあしらわれている金唐革紙などの壁紙も部屋によって雰囲気が違うので、ぜひ注目してみてください。


こちらが、2階南東の客室です。先ほどの客室より、さらに豪華な雰囲気の内装に仕上がっています。この部屋には、金唐革紙ができるまでの過程が展示されているので着目してみましょう。


こちらが、2階のベランダ。現在では周辺のビルを望めますが、当時は周辺に高い建物がなく、晴れた日には富士山や房総半島を見渡すことができたそうです。

2階には、2025年の3月に公開されたばかりの部屋があります。ここでは、金唐革紙の作品が展示されています。この部屋の窓からは、庭園の大きなイチョウの木がよく見え、黄葉の際に一番いい眺めが期待できるスポットだそうですよ。
和館には甘味処も。中庭を眺めながら抹茶で一服

洋館を見学し終わったら、次は和館へ。「旧岩崎邸庭園」の和館は、木造の書院造りを基調とした純和風建築で、岩崎家が日常的に過ごしていた私邸部分です。洋館が主に来賓を迎える「迎賓空間」だったのに対し、和館はよりプライベートな「生活空間」として使われていました。豪華な洋館とは対照的に、質素な和館には引き算の美が感じられます。天井には、今ではなかなか手に入らない、節目のない1本の木が使われているそうです。

奥のふすまには、明治を代表する日本画家・橋本雅邦(はしもとがほう)が描いたと伝えられる障壁画などが残っています。

和館には、実際にお茶や甘味をいただくことができるスペースがあります。洋館をぐるりと見学したら、ここで一息。

丁寧に立てられた抹茶と、埼玉県にある「老舗菓匠 花見」の季節の練り切りでひと休み。歩いて少し疲れた体に、抹茶の心地よい苦味と練り切りのやさしい甘さがしみます。

冬の寒い季節は障子が閉められていますが、季節がよくなると障子が開けられ、日本庭園を眺めながら休憩することができます。日本庭園とその奥に見える洋館のコントラストもすばらしく、風情があります。

お茶をした後は、和館を少し見学しましょう。完成当時は、洋館よりも和館のほうがはるかに広かったそうですが、現在では取り壊しを経て一部のみが残っています。部屋の各所には三菱財閥のシンボルである「菱紋(ひしもん)」がモチーフとなったしつらえが見られ、ふすまには富士山の絵も見られます。部材のひとつひとつは、現在では入手困難な木材。当時の様子そのままを、じっくり観察しましょう。
「旧岩崎邸庭園」には、今では想像もつかないほど豊かで華やかな明治の暮らしが息づいています。マナーを守ったうえで、平日は建物の写真撮影がOK(階段上での撮影、人物撮影や持込み品の撮影は不可。なお、土・日曜、祝日は館内すべて撮影禁止)。明治時代の暮らしに思いを馳せつつ、フォトジェニックな場所を探してみるのもいいですね。
Text:松崎愛香
Photo:斉藤純平
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。