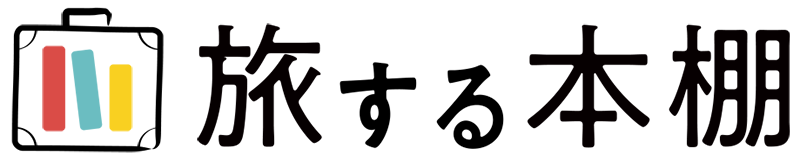江戸前そばのつゆはなぜ黒い? 知るほどにおいしい! そば、鰹節、佃煮を食べて、江戸食文化にふれる東京ガストロノミーツーリズムへ
そばや鰹節、佃煮…。どれも江戸で発達して現在も親しまれる日本人のソウルフードです。東京でいまも残る江戸食文化のルーツをたどり、食べて、体感する、東京ならではのガストロノミーツーリズムを体験してみませんか。今回は食のジャーナリスト・マッキー牧元さんの案内で、タレント・田中律子さんが江戸食文化を感じられるスポットを巡ります。なぜ江戸っ子に愛されたのか歴史背景を知ると、先人たちや現代の作り手をさらにリスペクトできて、おいしさも倍増! 江戸食文化にどっぷり浸かる食べ歩きツアーに出発です。
削りたては香りもうま味も別格! 鰹節尽くしの朝ご飯を/渋谷「かつお食堂」

まずは削り節をのせた炊きたてご飯、カツオ出汁のきいた味噌汁といったザ・ニッポンの朝ご飯で腹ごしらえ。
和食に欠かせない鰹節。材料となるカツオは、江戸時代には「女房を質に入れても初ガツオ」なんて川柳に詠まれたほど、江戸っ子に珍重されていました。というのも、カツオが獲れる駿河湾から新鮮なまま輸送するのが難しく、高価だったから。
一方、鰹節の原型は室町時代からあったといわれ、燻して水分が抜け固くなり、カビ付けして熟成された本格的な鰹節が作られるようになったのは江戸時代から。これによって長距離輸送ができるようになり、江戸っ子の食生活に鰹節が加わりました。

鰹節が主役の定食を食べに訪れたのは、JR渋谷駅新南改札から徒歩7分ほどの場所にある「かつお食堂(かつおしょくどう)」。ビルの地下1階、カウンター11席のみの隠れ家的な雰囲気ですが、国内外からお客さんが連日訪れる人気店です。営業は8時30分~13時30分で、13時過ぎに売り切れることもあるので、来店前には公式サイトから予約を。

店主は鰹節伝道師・かつおちゃんこと、永松真依さん。鰹節を削るおばあさまの凛とした姿に魅了されたのをきっかけに、鰹節愛に目覚め、産地を巡って、歴史や製法、カツオの漁法、生態などを学び、2017年に「かつお食堂」をオープンさせました。

定食を待つ間には永松さんがカツオや鰹節の魅力をイキイキと語ってくれます。鰹節を削ったり、金づちでカンナ刃を調整したりする小気味いい音が響き、まるでライブパフォーマンスのよう。

メニューは「かつお食堂の定食」のみ。「鰹節の一番おいしい食べ方は、削りたてを白いご飯にのせて食べること」という永松さんが、本枯節を1人前ずつその場で削って提供してくれます。炊きたてご飯の湯気に踊る鰹節は、息を吐けば飛びそうなほど極薄でふわふわ。まずは華やかな香りを楽しみ、一枚つまんで口に広がるうま味を感じて。その後は、天然塩や醤油麹を足して、卵かけご飯にしてと、お好みでどうぞ。
カツオ出汁でとった味噌汁はもちろん、もずく酢の三杯酢、鰹節ご飯の下に隠れたふりかけ、季節の野菜を使ったおかずと、すべての料理に鰹節が使われています。鰹節の奥深さや多彩な食べ方を知って、命に感謝して無駄なくいただくという昔から培われている日本の心を再認識できます。

江戸の粋とは、力強さやたくましさ、色っぽさをあえて表に出さないものだと考察した哲学者がいますが、目立たずともおいしさを影で支えるカツオ出汁文化にも江戸の粋を感じます。
■かつお食堂(かつおしょくどう)
住所:東京都渋谷区鶯谷町7-12 GranDuo渋谷 B1F
TEL:03-6877-5324
営業時間:8時30分~13時30分
定休日:毎月1日、水・木曜
江戸指物工房に弟子入り⁉ 伝統工芸士直伝の箸づくり体験/蔵前「茂上工芸」

お次は江戸指物の工房で、マイ箸づくりを体験しましょう。
江戸指物(えどさしもの)とは、金釘を使わずに、表面から見えない部分にほぞという凸凹を作って精巧に組み合わせた、江戸時代発祥の日本の伝統的な木工和家具のこと。薄い板を組み合わせるため、見た目は華奢ですが、頑丈なのが特徴です。茶道文化とともに発展し、華麗な装飾を施す京指物に対して、江戸指物は木目や色合いなど木本来の美しさを生かしたシンプルで粋な仕上がり。生活調度品として、武家や商人、歌舞伎役者に愛用されてきました。

蔵前にある江戸指物の工房「茂上工芸(もがみこうげい)」は、大正元年(1912)の創業で、現在は3代目の茂上豊さんが技術を受け継いでいます。茂上さんはこの道50年、経済産業大臣が認定する伝統工芸士の一人。伝統の技を踏襲しつつ、現代のライフスタイルに合わせた使い勝手のいいモダンな江戸指物家具を得意としています。
茂上さんの信条は、お客様に喜んでもらい、100年でも200年でも代々使えるものを作ること。職人技が駆使された江戸指物は、丈夫なのはもちろん、修理しながら長く使えて、使い込むほどに艶と輝きを増し、経年変化も楽しめます。
商品はたんす、引き出し箱、鏡台といった家具から、名刺入れやペンケース、木製ネクタイといった小物雑貨まで多種多彩。1階ショールームで展示販売されているほか、オーダーメイドの依頼や家具の修繕にも対応してもらえます。

箸づくりは、木材の特徴やカンナの扱い方といった基本を学ぶため、指物師が弟子入りしてはじめに習う作業だそう。江戸時代にも日常的に使われていた箸を、伝統工芸士に教わりながら作ってみましょう。
まず木材選びからスタート。カエデやタモ、ナラ、ヒノキ、マツなど5~6種類から、色や木目を見て、感触を確かめ、香りを嗅いで、選んでみて。
手のサイズに合わせて出来上がりの長さを決め、小さなカンナで少しずつ削っていきます。四角い面の角を均等に削り、徐々に丸に近づける繊細な作業に、おしゃべりも忘れて全集中! 茂上さんが随時アシストしてくれ、伝統工芸士のカンナ使いが至近距離で見られるまたとない貴重な体験です。

紙やすりでなめらかにして、えごま油を染みこませた布で拭き上げ、艶を出したら完成です。写真は田中律子さんが作った赤松のお箸で、赤みを帯びた木目が際立つ美しい仕上がりに! 日常でのお手入れ方法は、長時間水に浸けず、よく乾かすこと。また時々オリーブオイルを塗って、乾いた布で拭くと艶が出るのだそう。

■茂上工芸(もがみこうげい)
住所:東京都台東区蔵前4-37-10
TEL:03-3851-6540
営業時間:1階ショールームは9~17時
定休日:1階ショールームは土・日曜、祝日
体験:「箸づくり体験」江戸指物の箸箱付き(毎週水曜・土曜(不定期)の10時~11時30分に開催、所要時間約90分、7日前までにサイトから要予約)
江戸っ子を気取って、小粋にそばをたぐる/神田「室町砂場 日本橋本店」

箸づくり体験を通じて江戸指物師の技を間近で体験したあとは、江戸っ子気分でそば屋さんの暖簾をくぐります。
実は江戸中期まではそばよりもうどんが好まれたとか。そば食が広まった理由には、そばは痩せた土地でも年3回収穫できるため幕府から栽培を推奨され、そば粉に小麦粉を加えて食べやすくしたことなどがあります。
また、江戸幕府による天下普請で地方から集まった職人、参勤交代で諸国から出仕した武士は男性単身者が多く、自炊をしないため、屋台で手早く食べられるそばや寿司、天ぷらが浸透し、江戸の代表的な食文化となりました。さらに肉体労働で汗を流す職人は塩分を求め、千葉県の野田や銚子で作られはじめた濃口醤油を使ったそばつゆが好まれたのです。

「室町砂場(むろまちすなば)」は、江戸時代末期に麹町にあったそば店から暖簾分けして、日本橋に店を移した明治2年(1869)を創業年としている老舗。JR神田駅徒歩3分の場所に日本橋本店があります。
風情ある坪庭から自然光がさし込む店内にはテーブル席と小上がりがあり、老舗にふさわしい落ち着いた雰囲気です。

そばは2種類あり、そばの実の芯だけを挽いた更科粉を卵でつないだ「ざる」は、のど越し滑らか。そばの実を殻付きのまま引いたそば粉を二八の割合でつないだ「もり」は、そばの豊かな風味が楽しめます。

そばつゆはキレのあるカツオ出汁に、濃口醤油のかえしを使った辛口仕上げ。辛口ゆえに、麺の下部1/3ほどをつゆに浸せば十分で、これが江戸前の粋なお作法。また、ずずっと空気と一緒に麺をすすることで、そばの香りがより楽しめます。
そばの風味を堪能するため、香りが強いネギ&わさびの薬味は、そば湯をいただく時までキープしましょう。味変でわさびを使いたい場合は、つゆには加えず、麺に少しずつのせて、そばとわさびの香りを両方感じてみて。

温かいそばに板海苔の浅草海苔を磯の花に見立てて散らした「花まき」は、江戸時代から食べられてきた東京ならではの食文化を代表する一品。ふた付きの丼で提供されるのも粋な演出で、ふたを取ると豊かな磯の香りがふわりと漂います。

■室町砂場 日本橋本店(むろまちすなば にほんばしほんてん)
住所:東京都中央区日本橋室町4-1-13
TEL:03-3241-4038
営業時間:11時30分~21時(酒類20時LO)、土曜は11時30分~16時(酒類・料理ともに15時30分LO)
定休日:日曜、祝日
昔ながらの手法を守り抜く老舗の佃煮をおみやげに/新橋「新橋玉木屋 新橋本店」

仕上げに江戸時代から伝わる保存食、佃煮をおみやげに買って帰りましょう。
佃煮が江戸っ子に親しまれるようになったのには、徳川家康と深いかかわりがあります。本能寺の変で身の危険を感じた家康は摂津の国(大阪)の佃村という漁村にたどり着き、村人の助けを借りて逃げ延びます。家康はそれに感謝し、佃村の漁民に全国無税で漁ができる権利を与えました。漁民たちはその後、江戸へ移住。故郷の名前をとった佃島で、獲れた魚の残りの小魚を醤油で煮て、保存のきく惣菜として売り出したものが、佃煮として評判になりました。

「新橋玉木屋(しんばしたまきや)」の創業は天明2年(1782)、10代将軍徳川家治の時代。禅宗の僧侶から黒豆を砂糖で煮ることを教わった初代が「座禅豆」を売り出しました。その後、3代目が佃島の佃煮に目をつけ、製法に独自の工夫を重ねて、味・香り・艶のいい佃煮が開発されます。
創業から240余年、現在はあみやあさり、細切昆布、帆立貝、かつお角煮など、種類も豊富に。アイテム数は増えても、丹念な作り方は変わらず、素材ごとにタレを変え、材料や天候の細かな差異を考慮し、伝統に裏付けされた昔ながらの手作業で作っています。

一番人気は小さなエビに似た甲殻類の「あみ」。国内の淡水湖で獲れた希少なイサザアミを使っています。白だしのような味わいで、卵かけご飯の醤油代わりに、バゲットにのせて、パスタにからめてと、伝統的な佃煮も現代的なアレンジで楽しめます。

日本古来の食文化であるおにぎりを、自慢の佃煮やふりかけを使って作る「おにぎりワークショップ」も開催しています。訪日外国人に人気ですが、日本人でももちろん参加OK。インストラクターの先生からおにぎりとおむすびの違いを教わった田中律子さんも、「日本人でも知らない人は多いかも、ぜひ参加してほしい」とイチオシ。

つやつやの白米、生姜まぐろ・あさり・お茶漬の友の佃煮、うなぎ山椒・梅かつお・帆立貝のふりかけが用意され、2個のおにぎりを作ります。具材を真ん中に配置するコツや、口でほわっとほどける三角形&俵型の握り方など、おにぎりづくりの基本を改めて知り、発見がいっぱい。完成品はその場で食べても、持ち帰っても!

■新橋玉木屋 新橋本店(しんばしたまきや しんばしほんてん)
住所:東京都港区新橋4-25-4
TEL:03-6450-1231
営業時間:10時~18時30分、土・日曜、祝日は10~18時、飲食カウンターは全日11~18時(LO17時30分)
定休日:無休
体験:「おにぎりワークショップ」佃煮・ふりかけ・おにぎり型のおみやげ付き(営業時間内に開催、所要時間約90分、電話・公式サイトから要予約)

知っているようで、実は知らないことばかりの江戸食文化。マッキー牧元さん&田中律子さんが巡ったツアーをなぞって、ぜひ食べて体験してみて。東京には、江戸の食文化を受け継ぐ老舗や、新たな視点で食文化を発展させるスポットがまだまだたくさん。都内各地を巡って、東京の食の魅力を再発見しましょう♪
Text:伊藤あゆ
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
Sponsored:東京都