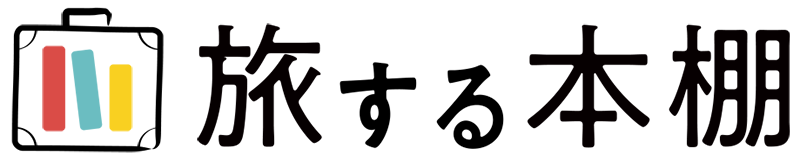お参りの仕方|神社7ステップ・お寺4ステップで正しい参拝を
神社やお寺での正しいお参りの仕方を知っていますか?お参りの仕方を覚えておけば、初詣や観光、大切な願いごとをする際にも不安なく参拝できます。今回は、神社とお寺、それぞれのお参りの仕方について、基本の流れや作法の違いを解説。お賽銭の金額や願いごとの伝え方、参拝時のタブーなどもあわせて説明するので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
お参りの仕方|神社とお寺の違い

お参りの仕方は、神社とお寺で大きく異なります。
神社では「二礼・二拍手・一礼」を行うのに対し、お寺では拍手をせず静かに合掌するのが基本。また、神社には鳥居があり、お寺には山門があるなど、入口の作りも違います。
これらの違いを理解しておくことで、それぞれの場所で正しいお参りの仕方ができるようになります。初めて訪れる場所でも迷わず参拝できるよう、基本的な違いを押さえておきましょう。
神社とお寺で作法が異なる理由
神社とお寺でお参りの仕方が違うのは、お祀りしている対象が違うためです。
神社では日本の神様を、お寺では仏様をお祀りしています。対象が違うため、それぞれに適した敬意の表し方も変わってくるのです。
神社の拍手は音を立てることで、神様に存在を知らせる意味があります。一方、お寺では仏様の前で静かに心を整えることを重視するため、音を立てずに合掌します。このように、誰に向かって祈るかによって作法が決まっているんですよ。
神社は神道、お寺は仏教
神社は神道の施設で、お寺は仏教の施設という違いがあります。
神道は日本で古くから信仰されてきた宗教です。自然や祖先を神様として崇め、山や川、木などにも神様が宿っていると考えられています。
一方、仏教はインドから中国を経て日本に伝わった宗教です。お釈迦様が説いた教えに基づき、煩悩を取り除いて悟りを目指します。この宗教の違いが、建物の名称や参拝方法の違いにつながっているんです。
神社のお参りの仕方|基本の流れ

神社でのお参りの仕方には、正しい手順があります。
鳥居をくぐるところから始まり、手水舎での清め、拝殿での拝礼まで、ひとつひとつの所作に意味が込められています。基本の流れを押さえておけば、どの神社を訪れても失礼なくお参りできるようになりますよ。
神社でのお参りの仕方は大きく分けて下記の7つのステップ。
●STEP1:鳥居で一礼
●STEP2:参道は端を歩く
●STEP3:手水舎で手と口を清める
●STEP4:お賽銭を納める
●STEP5:鈴を鳴らす
●STEP6:二礼・二拍手・一礼
●STEP7:願いごとを伝える
それぞれ詳しく説明していきます。
STEP1:鳥居で一礼
神社の入口にある鳥居の前で、まずは一礼を。
鳥居は神様の領域と人間の世界を分ける境界線です。これから神聖な場所に入らせていただくという気持ちを込めて、しっかりと一礼しましょう。
鳥居をくぐる際は、真ん中を避けて端を通るのがマナーです。
STEP2:参道は端を歩く
参道を歩くときは、中央を避けて左右どちらかの端を歩きます。
参道の真ん中は神様の通り道とされているため、人が歩くのは避けるべき場所です。ゆっくりと落ち着いた気持ちで歩くことで、これから参拝するという心構えができていきます。
STEP3:手水舎で手と口を清める
拝殿に向かう前に、手水舎で手と口を清めます。
まず右手でひしゃくを持ち、左手を洗います。次にひしゃくを左手に持ち替えて右手を洗いましょう。再び右手にひしゃくを持ち、左手に水を受けて口をすすぎます。最後に左手をもう一度洗い、ひしゃくを立てて柄の部分に水を流して元の場所に戻します。
STEP4:お賽銭を納める
拝殿の前に着いたら、賽銭箱にお賽銭を納めます。
お賽銭は神様への感謝の気持ちを表すもの。金額に決まりはありませんが、5円玉を「ご縁」、50円玉を「五重のご縁」として語呂合わせで縁起を担ぐ人もいます。静かにそっと賽銭箱に入れましょう。
STEP5:鈴を鳴らす
お賽銭を納めたら、拝殿にある鈴を鳴らします。鈴は神様に自分が来たことを知らせ、場を清める意味があります。鈴緒をしっかり持って鳴らしましょう。回数は神社によって異なりますが、一般的には2~3回程度です。
鈴がない神社もあるため、その場合は省略して問題ありません。
STEP6:二礼・二拍手・一礼
鈴を鳴らしたあと、二礼・二拍手・一礼の作法で拝礼します。
まず深く2回お辞儀をします(二礼)。次に胸の高さで手を合わせ、右手を少し下にずらして2回拍手します(二拍手)。
この作法は多くの神社で共通していますが、「伊勢神宮」(八礼・八拍手)や「出雲大社」(二礼・四拍手・一礼)など、一部の神社では異なる作法が用いられています。参拝前に案内板などで確認するとより安心です。
STEP7:願いごとを伝える
二拍手のあと、手を合わせたまま心の中で感謝と願いごとを伝えます。
まずは日頃の感謝や無事に過ごせていることへのお礼を伝えましょう。そのあと、自分の願いごとを具体的に心の中で伝えます。
感謝と願いを伝え終わったら、最後に深く1回お辞儀をして(一礼)拝礼は完了です。
お寺のお参りの仕方|基本の流れ

お寺でのお参りの仕方は、神社とは異なる作法があります。
ここでは一般的な作法を紹介します。神社との大きな違いは、拍手をせず静かに合掌すること。基本の流れを押さえておけば、初めてのお寺でも落ち着いてお参りできるようになりますよ。
お寺でのお参りの仕方は大きく分けて下記の4つのステップです。
●STEP1:山門で一礼
●STEP2:手水舎で手と口を清める
●STEP3:お賽銭を納める
●STEP4:合掌して拝礼(拍手なし)
それぞれ詳しく説明していきます。
STEP1:山門で一礼
お寺の入口にある山門の前で、まず一礼をします。
山門は仏様の領域への入口。これから神聖な場所に入らせていただくという気持ちを込めて、深く一礼しましょう。
山門をくぐる際は、敷居を踏まないように注意してください。
STEP2:手水舎で手と口を清める
本堂に向かう前に、手水舎で手と口を清めます。
清め方は神社と同じです。右手でひしゃくを持ち左手を洗い、ひしゃくを左手に持ち替えて右手を洗います。再び右手にひしゃくを持ち、左手に水を受けて口をすすぎましょう。最後に左手をもう一度洗い、ひしゃくを立てて柄の部分に水を流して元の場所に戻します。
心身を清めて仏様の前に立つための大切な準備です。
STEP3:お賽銭を納める
本堂の前に着いたら、賽銭箱にお賽銭を納めます。
お賽銭は仏様への感謝の気持ちを表すものです。金額に決まりはありませんので、自分の気持ちに応じた額で問題ありません。静かにそっと賽銭箱に入れましょう。
STEP4:合掌して拝礼(拍手なし)
お賽銭を納めたら、静かに合掌して拝礼します。
胸の前で両手を合わせ、目を閉じて心を落ち着けます。日頃の感謝や願いごとを心の中で静かに唱えましょう。
お寺では拍手はせず、静かに手を合わせることで仏様への敬意を表します。宗派やお寺によって焼香などの作法が異なる場合もあるため、案内に従いましょう。祈りが終わったら、深く一礼して本堂を後にしましょう。
お参りの仕方で注意したいタブー

お参りの際には、避けるべきタブーがいくつかあります。
神社やお寺は神聖な場所のため、失礼のないように基本的なマナーを守ることが大切です。ここでは、特に注意すべき4つのタブーについて説明します。
参道の真ん中を歩く
参道の真ん中は神様の通り道とされているため、歩いてはいけません。参道を歩く際は、必ず左右どちらかの端を歩くようにしましょう。真ん中は「正中」とよばれ、神様が通る神聖な場所です。
端を歩くことで、神様への敬意を示すことができます。
帽子を脱がずに拝礼する
拝殿や本堂の前で拝礼する際は、帽子を脱ぐのがマナーです。帽子をかぶったまま神様や仏様の前に立つのは失礼にあたります。サングラスや日傘も同様にNGです。
境内を歩く際は帽子をかぶっていても問題ありませんが、拝礼の際は必ず脱ぐようにしてください。
大声で話す・騒ぐ
神社やお寺の境内で大声で話したり、騒いだりするのは避けましょう。
神聖な場所では静かに落ち着いた態度で過ごすことが大切。友人や家族と一緒でも、声のトーンを抑えて会話しましょう。心を落ち着けて参拝することで、より良いお参りができます。
肌の露出が多い服装
タンクトップやショートパンツなど、極端に肌の露出が多い服装、ビーチサンダルなどラフすぎる履物は避けた方が望ましいです。普段着で問題ありませんが、清潔感を意識した服装を選びましょう。
お参りの仕方でよくある疑問
お参りの仕方について、多くの人が疑問に思うポイントがあります。ここでは、お賽銭の金額や願いごとの伝え方など、よくある3つの疑問にお答えします。
お賽銭の金額はいくらが適切?
お賽銭の金額に明確な決まりはありません。
自分の気持ちに応じた額で問題ありませんが、5円玉を「ご縁」、50円玉を「五重のご縁」として語呂合わせで縁起を担ぐ人もいます。感謝の気持ちがあればどの金額でも構いません。
願いごとはどのように伝える?
願いごとを伝える際は、まず感謝の気持ちを伝えることが大切です。
日頃の無事や健康への感謝を述べたあと、願いごとを具体的に心の中で伝えましょう。願いごとは欲張らず、ひとつかふたつに絞って丁寧に伝えるのがよいとされています。
連続してお参りしても大丈夫?
同じ神社やお寺に連続してお参りすることは、基本的には問題ないとされています。
定期的にお参りすることで神様や仏様とのご縁が深まるという考え方もあります。ただし、宗派や地域によって解釈が異なる場合もあるため、気になる方は神社やお寺に確認すると安心。
お参りの仕方で大切な心構え
形式を守ることも重要ですが、どのような気持ちでお参りするかが最も大切だといえます。お参りの際は、神様や仏様への敬意と感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
願いごとをするだけでなく、日頃の無事や健康に対する感謝を伝えることが大切です。「ありがとうございます」という気持ちを込めて参拝することで、より心のこもったお参りができます。感謝の気持ちを第一に、謙虚な姿勢で神様や仏様と向き合いましょう。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。