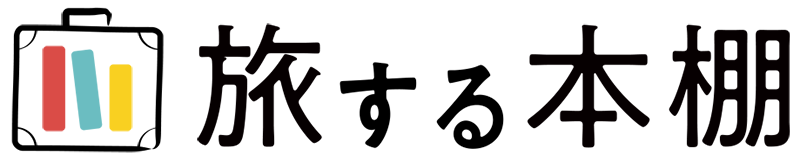京都「伏見・醍醐・宇治エリア」のおすすめ初詣(2026)伏見稲荷大社など
あけましておめでとうございます。2026年の始まりは初詣に出かけませんか。伏見稲荷大社など、京都の伏見・醍醐・宇治周辺エリアで初詣におすすめのスポットをご紹介。各寺社の由来や初詣行事、「厄除け、開運、商売繁盛、交通安全…」などの主なご利益、お正月の混雑時間などをチェック。2026年のお正月にお参りしたいスポットを探してみて。
総本山 醍醐寺(京都府/京都市伏見区)
醍醐山全山を寺域とする京都屈指の大寺院で、真言宗醍醐派の総本山。山上の上醍醐と山下の下醍醐に分かれ、50余の堂塔が点在。貞観16年(874)に修験道中興の祖である聖宝理源大師が開き、第80代座主・義演僧正の時代、豊臣秀吉の尽力により再興した。下醍醐の伽藍に立つ国宝の金堂や五重塔をはじめ、数多くの文化財を有し、世界文化遺産「古都京都の文化財」にも登録されている。豊臣秀吉が慶長3年(1598)に、盛大な「醍醐の花見」を催したことでも知られる桜の名所で、秋の紅葉も見ごたえがある。

初詣期間の情報
1月1~3日は9時~16時30分(三宝院は閉門30分前受付終了)、伽藍は拝観無料、三宝院は本堂に参拝できる特別拝観を実施。霊宝館は閉館。
初詣行事
● 年頭式/2026年1月5日/柴燈護摩道場で初祈祷・初柴燈護摩供が行われる
● 初聖宝会/2026年1月6日/上醍醐の開山堂で、醍醐寺開山の理源大師を供養する法要が行われる
- ご利益:安産子育て、無病息災、商売繁盛、その他、開運招福全般、災難除け、子授け
- 宗派・ご本尊:真言宗醍醐派/薬師如来坐像
- 料金:三宝院・伽藍・霊宝館3カ所共通券大人1500円。1カ所券、2カ所共通券、三宝院特別拝観券、春期(3月20日~4月第3日曜)については公式サイト要確認。上醍醐入山無料
- 駐車場:あり/有料
- URL:https://www.daigoji.or.jp/
萬福寺(京都府/宇治市)
日本三禅宗の一つ黄檗宗の大本山で、日本に「いんげん豆」をもたらした明末の渡来僧隠元[いんげん]禅師が江戸時代初期に開いた。明朝時代の中国建築様式を取り入れた建物や、お経に節をつけて読む梵唄に儀式作法など、随所に中国風を伝える。鉄木とも呼ばれる硬いチーク材を用いた大雄宝殿(本堂)は、現存する木造建築の中でも世界に類を見ないもの。創建当初の姿をよく残し、大雄寶殿、天王殿、法堂の三棟は国宝に指定され、その他の伽藍建築群も重要文化財に指定される。境内では隠元が伝えた中国風の精進料理「普茶」3300円~が食せるほか、坐禅1000円や写経2000円の体験も可能。

初詣期間の情報
参拝時間は12月31日22時~1月1日1時30分。境内参道には行灯が並べられ、除夜の鐘つきに、年越しそば販売、厄除け茶が無料で振舞われる。新年最初の行事である大般若経六百巻転読法要では多勢の人が本堂に訪れる。一年の厄除け・招福の祈祷を受けることもできる。
初詣行事
● 除夜の鐘撞き/2025年12月31日受付開始23時、鐘つき開始23時45分/108の煩悩を打ち払い新年を清らかな気持ちで迎えるための行事
● 新年の二字/2026年1月1日0時~/例年の「今年の漢字」に対して新年の希望の二字を高僧が揮毫
● 大般若経六百巻転読法要/2026年1月1日0~1時/大般若経六百巻を転読して、一年の厄除けと招福を祈願する
- ご利益:無病息災、その他、諸縁吉祥、金運来福、開運招福
- 宗派・ご本尊:黄檗宗/釈迦如来
- 祭神:布袋尊(都七福神)
- 混雑時間:1月1~3日と最初の土・日曜は終日混雑
- 料金:拝観高校生以上500円、小・中学生300円
- 駐車場:あり/1時間30分600円、以降30分毎200円/12月31日は1台1000円
- URL:https://www.obakusan.or.jp/
平等院(京都府/宇治市)
平安後期の永承7年(1052)に、関白・藤原頼通が父・道長の別荘を寺に改めたのが始まり。平安貴族が夢見た極楽浄土を形にした鳳凰堂(国宝)は十円玉にも刻まれ、その優美な姿はあまりにも有名。当初は広大な伽藍を誇ったが戦火で大半を焼失。現在残るのは、阿字池の中島に立つ、天喜元年(1053)に建立された阿弥陀堂の鳳凰堂だけ。鳳凰堂を含む浄土式庭園は国指定名勝・史跡だ。境内にある鳳翔館では国宝の梵鐘や屋根の鳳凰などを展示。鳳凰堂の内壁を飾った雲に乗って楽器を奏でる雲中供養菩薩像も半数の26体が展示されている。

(C)平等院
初詣期間の情報
1月1~3日も通常通りの拝観時間。開門8時45分、閉門17時30分(17時15分受付終了)。
- ご利益:
- 宗派・ご本尊:単立/阿弥陀如来
- 混雑時間:1月1~3日は終日混雑
- 料金:拝観大人700円、中・高校生400円、小学生300円。鳳凰堂内部拝観は別途志納金
- 駐車場:なし/近隣に駐車場あり/駐車場なし。周辺に民営の駐車場あり。交通規制等なし
- URL:https://www.byodoin.or.jp/
石清水八幡宮(京都府/八幡市)
緑豊かな男山の山上に立つ古社で、創建は貞観2年(860)。国家鎮護のために、平安京の裏鬼門(南西)に当たるこの地に九州宇佐より八幡神を勧請されたのが始まり。創建以来朝廷の崇敬は篤く、のちに源氏の氏神となり源頼朝らも訪れたという。現在は厄除けの神様として信仰を集める。朱塗りの社殿は徳川家光の寄進により江戸時代に再建され、動物彫刻などで装飾された豪華絢爛な本殿を含む十棟が国宝に指定。『徒然草』の有名な話で、仁和寺の僧が八幡宮本殿と間違えたという摂社、高良神社[こうらじんじゃ]は男山山麓にある。

石清水八幡宮
初詣期間の情報
開閉門、ご祈祷、授与所の時間:12月31日6~23時(祈祷受付は9~16時)、1月1日0~19時頃、2・3日は7時30分~18時頃。厄除け、家内安全、必勝の御神矢を受けて背中にさす参拝者の姿が風物詩となっている。
初詣行事
● 厄除大祭/2026年1月15~19日/古くは法会の期間とされ、この期間に多くの人が厄除け参りに訪れる
● 厄除大祭 焼納神事/2026年1月19日10時~/前年の古いお札をお焚き上げする神事で、その火で清められた「厄除餅」が無料で配られる(1000人)
● 鬼やらい神事/2026年2月1日15時/本殿前にて宮中に伝わる古式に則り節分行事が行われる。「鬼やろう」の掛け声とともに福豆がまかれる。参拝者には福豆が配られる
- ご利益:厄除け、安産子育て、交通安全、商売繁盛、その他、勝運
- 祭神:応神天皇、ひめおおみかみ、神功皇后ほか
- 混雑時間:1月1~3日は10~14時
- 料金:境内無料。春期:3~4月の土・日曜、祝日、秋期10~11月の土・日曜、祝日の14時、昇殿参拝1名3000円(行事により変更あり)
- 駐車場:あり/普通車1台500円、大型バス1台3000円※繁忙期は変更あり/1月1~3日は駐車場周辺の道路交通規制により駐車場利用不可
- URL:https://iwashimizu.or.jp/
一休寺(酬恩庵)(京都府/京田辺市)
一休禅師が晩年を過ごした寺。鎌倉時代、妙勝寺として創建。その後兵火に遭ったが、一休が康正年間(1455~56)に再興。酬恩庵と号した。苔に覆われ、しっとりと風情のある境内には本堂・方丈・庫裏(すべて重要文化財)が立ち、方丈庭園と虎丘庵庭園は名勝に指定。一休は81歳で大徳寺住職となった時もここから通い、88歳で没した。方丈中央に安置する木造一休禅師像(重要文化財)は逝去の年に高弟に作らせた等身大の像で、髪や髭は一休が自分のものを植え付けたという。一休禅師遺法といわれる一休寺納豆750円は庫裏で買える。

初詣期間の情報
参拝は1月1日9~17時。
- ご利益:学業成就、その他、合格祈願
- 宗派・ご本尊:臨済宗大徳寺派/釈迦如来坐像
- 料金:拝観大人600円、中・高生300円、小学生200円
- 駐車場:あり/普通車500円、小・中型バス700円、大型バス1000円
- URL:https://www.ikkyuji.org/
- 掲載の情報は予告なく変更になる場合がありますので、おでかけ前に現地にご確認ください